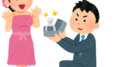「1994年、東京都生まれ」
2022年11月に刊行した小説『ジャクソンひとり』(河出書房新社)は、28歳の著者・安堂ホセさんにとって初の著作。第168回芥川賞(1月19日発表)の候補作にもノミネートされた記念すべき1冊だ。
にもかかわらず、巻末に載せた著者としてのプロフィールはたったのこれだけ。物語とは別に「あとがき」にあたるようなエッセイを入れるでもない。いくらページをめくっても、著者の人物像は断定できない。
「アフリカのどこかと日本のハーフで、昔モデルやってて、ゲイらしい」と職場で噂される「ジャクソン」を主人公として進む物語に、安堂さんはどのように向き合ったのか。インタビューで詳しく聞いた。
 撮影:金春喜 / ハフポスト日本版
撮影:金春喜 / ハフポスト日本版“孤独な当事者”が書いたのか?
プロフィールを最低限しか記さなかったのには、理由がある。
「マイノリティの著者がプライバシーを明かす。すると、本の表紙の上にさらにもう1枚、『こんなめずらしい人が書きました』とのメッセージが付されたカバーがかかることになります。
そのカバーが(著者と似た背景の)当事者を勇気づける可能性もあります。ですが、マジョリティ側の興味を満たすために貼られた“ラベル”になってしまうことも少なくありません。
そんなラベルのかかった本を見かけたら、私なら『さむい』と思うはず」
こうした思いもあり、自らのプロフィールや作品の内容についてどのような情報を表向きにアピールするか、刊行前から出版社の編集者とともに細心の注意を払いながら決めていったという。『ジャクソンひとり』の公式サイトでは冒頭、登場人物の属性には焦点を当てずに、内容をこう紹介する。
着ていたTシャツに隠されたコードから過激な動画が流出し、職場で嫌疑をかけられたジャクソンは3人の男に出会う。痛快な知恵で生き抜く若者たちの鮮烈なる逆襲劇!
 撮影:金春喜 / ハフポスト日本版
撮影:金春喜 / ハフポスト日本版 撮影:金春喜 / ハフポスト日本版
撮影:金春喜 / ハフポスト日本版それでも、刊行後に注目を浴びるにつれて目の当たりにすることになったのは、「こちら側だけに(著者のプライバシーを明かすかどうかについての)“ガイドライン”を置いていても意味がない」という現実。そこには、メディアが“当事者”をどのように見せようとしているかが垣間見えたという。
「著者である私を『孤独な当事者』と称した記事もありました。
『当事者(である著者)は孤独だ』という、あらかじめ用意したレッテルに当てはめたのだとしか読めませんでした。このときの取材は丁寧だっただけに、とても残念でした。
同様に、マイノリティをメディアが紹介するとき、最初からある“決めつけ”の中に二言、三言だけ当事者の声を埋め込むような形式がほとんどです。“かわいそうなもの”を扱うという前提で、ちょうどよく当てはまる“かわいそうさ”を持つ人の声だけを寄せ集めているのでは。
こうした描き方は、マイノリティの人々を搾取しているように見えます」
だから、安堂さんが参考にするのはメディアを通して“切り抜かれた声”ではない。当事者が自らSNSや抗議団体などを通して発信している内容を参照しながら、登場人物の人物像を練り上げていったという。
 撮影:金春喜 / ハフポスト日本版
撮影:金春喜 / ハフポスト日本版何かを訴えかけるシリアスさではなく…
ブラックミックスの男が裸で磔(はりつけ)にされた映像がジャクソンの勤め先の人々の目に触れるところから、物語は始まる。誰もが一目で男をジャクソンだと判断し、本人が否定しても信じない。
その後、ジャクソンは3人の「ブラックミックスの男」に出会う。その誰もがジャクソンと同じく、映像に映る人物と自分を見間違えられる経験をしていた。
ただ、こうした展開とは裏腹に、物語で目を引くのは、肌の色やセクシュアリティの似る男性4人それぞれの際立った個性だ。彼らは決して“同一人物”ではない。
「登場人物を“この社会に実際にいる人”として描きたかったからこそ、自分自身の目を通して、1人1人と向き合いました」
キャラクターの設定として4人の主語や語尾を固めることはせず、それぞれが親密に語り合ううちに言葉遣いが似通っていく様子まで再現したという。
「反対に、人格や行動の基準を“ストレートの人が思い描くゲイ像”に置きたくはなかった。特に、LGBTQ(性的少数者)の人々は悲劇を生きているーーそんなトーンで描くと最初から決めてしまえば、その“決めつけ”には当てはまらない実態を見えなくしてしまいます」
物語には、現実の社会で起きていることが写し出されている。実際に、メディアが黒人の著名人の顔や名前を間違えて報じることは後を絶たない。
公園にいたジャクソンが警察から受けた職務質問は「レイシャル・プロファイリング」と呼ばれ、実際に日本でも起きている。警察などの法執行機関が、人種や肌の色などの特定の属性を根拠に、個人を捜査の対象としたり、犯罪に関わったかどうかを判断したりすることを指す。
4人の「ブラックミックスの男」は、こうした現実の問題が迫ってくる日常を、物語の中で生きる。だが、もちろん、彼らの生活はそれだけで終わらない。仲間と和やかに語り合ったり、意見の相違にぶつかったり、1人の時間で何かに没頭したりーー。
「追い求めたのは、誰かに何かを訴えかけるシリアスさよりも、自分自身が日常生活で感じているテンションやバイブスと地続きで“ピッタリくるもの”。
フィクションの世界で生きている登場人物のリアリティを、読んだ当事者が味わってくれたら」
「ジャクソンがまたクレームを出した」
ジャクソンと全く同じ背景を持つわけではないが、在日コリアンの私にも、“ピッタリくるもの”を感じた描写があった。
 撮影:金春喜 / ハフポスト日本版
撮影:金春喜 / ハフポスト日本版スポーツブランドのスタッフ専用ジムで整体師として働くジャクソンは、こんなことを「ジムのリーダーでも(上司の)エイジでもなく、人事の男に直接メール」で伝える。
〈××さんに朝挨拶をしたところ『今日も黒いね』と言われ、笑われました。不快だったので注意していただけないでしょうか〉
〈先週施術に来た××さんという方から『ゲイだって疑惑でてるけどまじ?』と話しかけられました。プライバシーに関わる発言なので注意していただけないでしょうか〉
〈同じ日に施術に来た方から『やっぱ黒人のお尻って特別だよね』と言われ、触られました。気持ち悪いのでマッサージの使用を禁止して欲しいです〉
ジャクソンを「LGBTQ+」「(ルーツが)ミックス」「さらに近隣のアジア人でも白人でもない」「左利き」という「珍しさ」から贔屓していた上司・エイジはこうした報告を知り、最初は「ジャクソンが正しいんじゃない?」と反応する。
だが、徐々に「ジャクソンがまたクレームを出した」と、ジャクソンの肩を持つ気持ちが揺らいでいく。
エイジは、「××さん」たちに直接伝えずに人事を介する理由などをジャクソンに直接尋ねる。ジャクソンの答えは「僕に気分があっちゃダメですか?」「僕の感想は、関係ないと思います」。
「ジャクソンの心がどう痛んだのかを聞き出したかった」というエイジは、思い通りの返答を得られず「フェアじゃない」と感じ、贔屓してきた部下との間の「断絶」を認識する。
「本来“被害者”であるジャクソンによる報告の内容を知ったエイジ。度重なると、今度は逆に(ジャクソンを)“加害者”かのようにみなすようになる。
そんな“加害者”側の本音のダサさを、まるでスパイになったかのような気持ちで綴りました」
安堂さんがエイジとジャクソンの関係性に反映したのは、自分にとって憎い典型的な“加害者”ではなく、むしろ「自分にこれまでよくしてくれた上司や先輩」の存在だったという。
「信頼しきった相手に突然、差別的なことを言われたら、自分はすぐに反発できるのか。反発できずにむしろ丁寧な対応を返してしまうかも。実際には、心にグサリと刺さっているのに。そんな自分の弱さを思い返していました」
安堂さんとジャクソンを重ね合わせた一幕。“日本企業で数年働いた外国籍者”の私もまた、自らの経験をジャクソンに重ねて共感していた。
差別が生まれる瞬間は、それまでの関係性やお互いの気質にかかわらず、どんなところにもあるーー。そんなリアリティを、ジャクソンとエイジを通して感じるのだった。
 撮影:金春喜 / ハフポスト日本版
撮影:金春喜 / ハフポスト日本版観客に見せるための“復讐”ではない
エイジに対するジャクソンの態度や心情について、読み手が必ずしも共感するわけではないーー。安堂さんは、そう予測する。むしろ、エイジの考えに賛同する人もいるだろうと。
安堂さんは「世の中が(マイノリティや多様性をめぐる価値観を)アップデートしていけば、エイジとジャクソンの関係性をめぐる読者の捉え方も変わっていくのでは」と考えつつも、「これから先、後退する可能性もある」と懸念する。
「マイノリティに関心を持ってこなかった人々がここ数年、『多様性』という言葉そのものをディスり(批判し)始めています。多様性に関する情報が蓄積された結果、当事者の弱さや苦しみが、ありきたりに見えるのかもしれません」
この波は、文学界にも押し寄せているという。
「多様性をディスる人々が気がつくずっと前から、社会には多様な人々がいる。そのことを今さら自覚してなされる多様性にまつわる批判は、私からみると初歩的で、冷笑にすぎません。
『自分は問題提起をしただけ。読者が考えるきっかけになれば、それでいい』とでも言いたげなポーズをとる作家もいます。けれど、私は『有名作家が多様性について考えてくれただけでありがたい』とは思いません」
昨今のこうした風潮に同調したくないーー。そんな気持ちで描いたのが、物語の後半で成し遂げられる“復讐劇”。ジャクソンたちは自らに注がれる差別的な眼差しを逆手にとり、“復讐”を積み重ねていく。
「これは観客に見せるための“復讐”ではなく、彼ら自身のためのもの。仮に成功しなくても、彼らが飽きたらいつでもやめていい。私はあくまでも“5人目のジャクソン”にあたるような読者を1番に想定しています。妥協したくありません」
 撮影:金春喜 / ハフポスト日本版
撮影:金春喜 / ハフポスト日本版「学ぶものがある」「感動する」ような物語ではない。安堂さんは、自著をそう評する。
「筆をとったのは、『何かを伝えたい』というより、『こういう小説が、あってほしい』との思いがあったから。物語で描いた軋轢や諦念、あるいは幸福を、日々“当然のこと”として生きている誰かに届いてほしい」
安堂さん自身、小説を読むことを通して、「自分でも気づかなかった感情に気づかされる」経験をしてきたという。
「本当の意味で没頭できるフィクションは、当事者にとって大きな力になると思っています。
この本が誰かを劇的に救わなくても、誰かの日常の中にあったらうれしい。Netflixで傑作じゃない作品を、自分にちょうどいいテンションで観て、捨てていく。そんな風に、誰かに読み捨てられていってほしい。ピンとくる人が読んでくれたら、それが1番です」
〈取材・文=金春喜 @chu_ni_kim / ハフポスト日本版〉
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
「多様性について考えてくれただけでありがたい」とは思わない。『ジャクソンひとり』の“復讐”が意味するもの【芥川賞候補作】