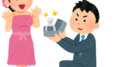8月に刊行されたジャーナリスト北丸雄二さんの最新刊『愛と差別と友情とLGBTQ+ 言葉で闘うアメリカの記録と内在する私たちの正体』(人々舎)が12月24日、「紀伊國屋じんぶん大賞2022」2位を受賞した。人文書の年間ベスト30を読者投票とともに選出する同賞。本書は、在米25年の北丸さんが東京新聞NY支局長として長年、在米生活を送った経験を生かし、現地で目の当たりにしたLGBTQ+ムーブメントの歴史や映画、LGBTQ+情報の日本における欠落を多岐にわたって検証している。ゲイのライター宇田川しい氏が、北丸さんにインタビューした。
北丸雄二(きたまる・ゆうじ) ジャーナリスト、コラムニスト。毎日新聞の記者としてキャリアをスタート。後に東京新聞に移り1993年、ニューヨーク支局長に。1996年に退社するも、そのままニューヨークに留まり、フリーランスのジャーナリストとしてアメリカのLGBTQ+に関する最新情報を日本に送り続けた。2018年、25年ぶりに帰国。精力的に執筆活動を続けるほか、ラジオでニュース解説も行っている。
「自分が何者であるか」に気づかないと、構造的な差別に気づかない

―― 「紀伊國屋じんぶん大賞2022」2位、おめでとうございます。快挙ですね。本書ではLGBTQ+を巡る様々な問題が論じられていますが、中でも「アイデンティティ・ポリティクス」と「ポリティカル・コレクトネス」という、弱者が声を上げるための武器についての論考が心に残ります。
アイデンティティ・ポリティクスは、今は、まるでマウントの取り合いのようになっているから、批判する人も多いんですよ。でも、まずアイデンティティを持たなきゃ始まらなかった歴史がある。女性にしろ、黒人にしろ、差別されている側は、自分たちは何者なのかと考え、女性という、あるいは黒人というアイデンティティに気づかざるを得なかった。自分たちが何者であるかということをまず、自分たちの足場にしなきゃならなかった。そこで初めて不正とか格差とか構造的な差別にも気づくことができたんだ。アイデンティティってね、そういう意味で必要なんですよ。
――ポリティカル・コレクトネスについても、「行き過ぎている」という批判があります。
確かに最近はポリコレがうるさいって言う人がいる。でも、もともと酷いコレクトネスがたくさんあって正しさを押し付けてきたのが歴史です。宗教的コレクトネスも白人至上主義もそうだったし、日本では家父長主義的なコレクトネスがあって人々を抑圧してきた。
奴隷制度はアメリカの荘園制度の中での正しさだった。そういうものに対抗するために抑圧された側が初めて手にした唯一の防衛手段、対抗手段がポリコレだったんだよね。抑圧されているすべての人にとっての自衛の武器。それはささやかな憤りであり、義憤とか公憤ともいうべきものにつながる。長いこと続いていた既存のコレクトネスは圧倒的に強大な大砲だったりしたんです。でもそれには、ポリコレが登場するまで誰も暴力的だなんて言わなかった。ポリコレ? 単なる棒ですよ。大砲に対して棒っこで対抗してるのにそれが行き過ぎだと批判するのはおかしくない?
――ポリティカル・コレクトネスにしろ、アイデンティティ・ポリティクスにしろ、アメリカではそれがマイノリティの武器として登場した歴史があって、その後、マジョリティの側がそれを批判する過程があった。でも、日本にはポリコレやアイデンティティ・ポリティクスの概念と同時に、それに対する批判も一緒に入ってきてしまった気がします。
ポリコレ、すなわち政治的に正しい言説って、公に通用する話ってこと。公的な言語っていうことなんです。日本は、そういうパブリックな話し方をあまり流通させてこなかったよね。「アレをナニして」みたいな、指示代名詞で意味が通じるような身内の言葉には長けているけど、それだと他者に話が通じない。他者を想定していない言語なんだ。身内だけの社会。
そこから他者である外国人への差別が生まれるし、女性やLGBTQ+という他者を想定していないから彼ら彼女らが異議を申し立てたときに、マジョリティの側は理解出来ずにたじろぐ。それで辻褄を合わせるために、「女やセクシュアルマイノリティが急に我が物顔でしゃしゃり出てきて特権を要求してる」みたいに受け取るんだよね。そういう、根底にある構造的で普遍的な問題に、LGBTQ+の話を通して気づけるんだよと示したかった。それがこの本を書いた目的の1つなんです。
この本はたまたまLGBTQ+の話を軸足にしてるけど、そこからだっていろんなものが見えてくる。(名古屋出入国在留管理局で収容中の3月に死亡したスリランカ人女性)ウィシュマさんの死や、ベトナム人技能実習生の酷い労働実態など、今、日本で吹き出しているいろんな問題とリンクしてくる。それは女性の問題であり、外国人の問題なんだけど、そういったマイノリティの問題は、マイノリティの側に問題があるのではなく、マジョリティの側にある問題なんだってことに、マジョリティが気づいていない、という問題なんですよ。

――女性やセクシュアルマイノリティに問題があるのではなく、それを「しゃしゃり出てくる」と感じてしまうことが問題ということですね。問題はマジョリティの側にある、と。
欧米ではそこに気づくマジョリティも多くなってきている。それは、LGBTQ+も、女性も多くの人がカミングアウトしているから。「女性もカミングアウトしている」の意味は、自分のアイデンティティを対抗的に主張しているということね。
マイノリティがアイデンティティを表明したときに、マジョリティの側も自分のアイデンティティに気づく。聞く側も「自分は男なんだ」「自分は異性愛者なんだ」って、合わせ鏡に映る自分の姿に気づく。つまりそれが「平等」と「入れ替え可能性」に気づくとっかかりになる。どっちかがマウントを取るんじゃなくフラットになる。きちんとアイデンティティを主張して、それがアイコ(五分と五分)なんだと気づいたときに、初めてアイデンティティ・ポリティクスは乗り越えられる。
――本に書かれている「マジョリティがマイノリティとの入れ替え可能性に気づく」ということですね。それまでマジョリティは常に語る側であり主語であったけど、マイノリティが主語を取り戻すことによって、マジョリティも語られる側、目的語になりうることに気づく。そして、それは「マジョリティにとっても常に主語であることからの解放なんだ」と。
そうそう、主語から解放されるのは楽しいことだよ、と。他者と入れ替え可能だと気づくことが、平等だと気づくことであり、相手を尊重することであり、愛することであり、友情につながっていく。自分と他者と立場が入れ替わった時にどんな思いをするのか考えることがアイデンティティ・ポリティクスを超克するんだよ。
だから、勝ち負けじゃない。闘うというより対抗する、カウンターなんだな。合わせ鏡のように相手に見せ合うことの重要性。
――例えば、在日コリアンの人々へのヘイトに対抗する、いわゆるカウンターと呼ばれる人がいます。ヘイターの激しい言葉に、同じように大声で対抗するスタイルは一部で批判も呼ぶわけですが。
そこには打ち負かそうっていう気持ちもあるかもしれないけど、基本は「同じ姿を見せてやる」ことなんだよ。
例えば、僕に「ゲイってどんなセックスするんですか?」なんてズカズカと聞いてくる奴がいるわけ。そうしたら「君はどんなセックスしてるの? 教えてくれたら僕も教えてあげる」って答える。それがカウンターだよ。自分が何を言ってるかに気づかせないといけない。カウンターは相手を逆照射する技術なんだ。
その技術を習得する過程で失敗もするだろうし、相手にギャフンと言わせたい気持ちも生まれるでしょう。その先、ギャフンと言わせた後どうなるのかという想像力を働かせることが必要なんだけど、いずれにせよカウンターの技術を得るために、最初は相手と競り合いをしなきゃいけない。
――やっぱり闘うことは必要。
闘う人がいなくちゃダメだね。みんながみんな闘わなくてもいいんだけど、闘う人もいないと話は前に進まない。ドッジボールと同じ。相手のボールをどんどん進んで取るやつがいる。懸命にボールをかわすやつもいる。いろんな役があってゲームが楽しく進む。カッカしてるばかりだと楽しくない。
LGBTQ+とは主語を奪われた屈辱感を代弁する言葉である

――本では、脱アイデンティティ・ポリティクスの方法論も書かれています。先ほどの「マウントの取り合いでなくフラットにする、アイコにする」部分です。その方法論を具体的に展開した部分がなかなか過激ですよね。ざっくり言うと「ノンケ(ストレート)の男も男とセックスしちゃえよ!」ていう(笑)。
MSM(Men who have sex with men)という人たちがいて、この人たちはゲイとは限らないけど男とセックスする。恋とか愛とか精神的なものなしに男とセックスする男がいるわけ。一方、多くのシスジェンダー(性自認と生まれたときに割り当てられた性別が一致している人)でヘテロセクシュアル(異性愛者)な男は、精神的紐帯で結ばれた男だけの集団に安住している。いわゆるホモソーシャルな関係だよね。
このホモソーシャルな集団は、MSMとは逆に精神的につながっているだけで肉体的なつながりを忌避してる。MSMとホモソーシャルは、まるで「ルビンの壺」(デンマークの心理学者エドガー・ルビンが考案した多義図形)のように地と図の関係なの。両者とも精神か肉体かのどちらかしかない。これは不幸ですよ。
――自分の中にある抑圧された同性愛的欲望に対して抱く恐怖が、ホモフォビアにつながっている。
ホモソーシャルは自分たちを解放すれば女性に優しくなれるし、MSMも精神性を獲得すると他の男たちに優しくなれるんじゃないかな。MSMとホモソーシャルが合体すれば男に対しても女に対しても友情が持てる。誰に対しても友愛的な関係が築けるようになる。でも、これは壮大な思考実験でね、実践出来る人と出来ない人がいる。才能が必要なんだよね。
――それで北丸さんは、「性には磁場の乱れみたいなものがあって、揺らぐものなんだから、別にゲイじゃなくても男とやることは特別なことじゃないし、怖がらなくていい。怖がらず男と寝ればラクになるよ」みたいな言い方で後押ししていますよね。いろいろ、すごいと思いました。脱アイデンティティ・ポリティクスというと、「お互い歩み寄って」みたいなことを言う人もいるんだけど、あくまで「こっち側に来い。それがお前らのためなんだ」と。
問題はマジョリティの側にあるからね。ストレートの側がちゃんとしろって話だから。というか、フーコーがそう言ってるのを、もうちょっと優しい言い方で援用させてもらったんです。
――違う意味で思い切ったこと書いていると思ったのは、「性には揺らぎがあって」という表現です。今のLGBTムーブメントの中で言いにくいことだったりもします。性的指向を理由にした差別を否定する時に、それは生まれつきで変えられないんだからというロジックが使われてきたから。また「思春期の男なんて射精することしか考えてないんだから男と寝たって不思議じゃないんだ」みたいなことも書かれていますけど、こういうのもジェンダー・バイアスが酷い印象があるから本来は言いにくいですよ。
本にも書いたけど、映画『君の名前で僕を呼んで』で、ティモシー・シャラメ演じる17歳の主人公エリオが、アプリコットを見てマスターベーションするシーンがあるんだよね。それで射精した後に泣くんだ、アプリコットで欲情してマスターベーションする自分はビョーキだって。あの苦しさだよ! 生理の苦しさとは違うけど、その切実さを通してしか、肉体性について男と女は分かり合えないんじゃないか。
これはインターセクショナリティ(人種や宗教、国籍、性的指向、性自認、階級、障害など、ひとりひとりの持つ属性や、それによる差別の構造は多層的で”交差”しているという考え方)とも関わってくる。違う者が交差してくる場所がある。セクシュアル・マイノリティについて言うと、互いの交差点がさっきも言った略奪されている主語性なんだよ。主語を略奪された思いはみんな一緒で、そこで連帯できる。
僕がLGBTQ+という時には、レズビアンやゲイやバイセクシュアル、トランスジェンダーといった個々の存在を代弁しているわけじゃない。ただ主語を奪われた屈辱感をこそ代弁しているつもりなの。
北丸少年が、闘う技術を身につけるために辿ったキャリア

――アイデンティティで言うと、北丸雄二という個人のアイデンティティの成り立ちについても興味があります。僕はゲイですけど、北丸さんと初めて会った時の第一印象って、「この人、ゲイっぽくないなあ」だったんですよね(笑)。
「北丸雄二似非ゲイ説」ってツイッターにあるからね(笑)。
――アメリカ生活が長いからでしょうか。新宿2丁目のコミュニティに染まっているタイプとは違うんです。そして、発言がちょっと権威的な印象がある。おそらく北丸さんは自分の主張に反論も当然来るという前提があって、フラットな関係性の上での発言だという意識があるのでしょう。現に反論に対してはちゃんと答える。Twitterで議論の前提すら理解してないようなアンチLGBTに何か言われても1回はちゃんとリプライを返す。優しいなあとも思いますけど、弱者を善導しようみたいな上から目線も感じます。僕自身は親戚のおじさんみたいな感じで好きですけどね。だから北丸おじさんと呼んでますが(笑)。
ああ、うん。おれ、エラそうなんだよね(笑)。でもそれって実はかなり戦略的で、現実世界のエラそうな異性愛規範社会に対して、私は対抗的に同じようにエラそうに言い返しているのだという自覚がある。もしくはそういう素振りだって私たちはできるんだぜとゲイ・コミュニティに示したいという意識もある。
――北丸さんが炎上しやすい理由の1つはそこなのかなと。新宿2丁目的なコミュニティに浸かって人格形成した人が、北丸さんみたいな、なんかゲイっぽくなくてエラソーな人がゲイについて語るのを見ると、それこそ主語を奪われたような気分になるんじゃないか、と。
うーん、一枚上手の収奪感なのか! でも、そういう対抗的キャラも必要なんだって思わない?(笑)。おれだって、もともとエラそうだったわけじゃないんだよ。若い時は文学少年だったのだ。21歳の時、文學界新人賞の最終選考まで残ったんだから!
――1984年に新潮社から『スタブロスは染まらない』という単行本の小説を出されてますね。とても繊細なSF純文学で、若き日の著者近影が美しくて、今と全然違うので驚きました(笑)。
あれを書いた当時は24で塾講師をしていて、巡りめぐって新潮社の手に渡ったときには「(毎月お金を払うから)小説家にならないか」って具体的に金額も提示されたんだけど、そう言われたときにはすでに28になっててもう新聞記者になってたんだよね。
――なぜ小説家にならなかったんですか。
うーん、新聞記者になることが必要だったんだと思う、自分の人生に。文学少年だった頃はさ、泣いてばかりいたのよ(笑)。小説を書くときはおれ、もう他のことできないし、暗〜い人間になるんだよ。小説って、人間の弱いところ、悲しいところを常に考えるみたいなところがあるわけ。まあ、いろんなタイプの作家がいるけど、おれはあのままだとダメになってたと思う。
――比喩じゃなくて、本当に北丸さんが泣いてたんですか?
そうだよ。15、6の時にはほんと、死にたいと思ってた。でも一方で、「死ぬな!」という声も頭の中で響いてた。おれ、自意識の目覚めは太宰治だったのね。太宰の「自意識の地獄」みたいなところから逃げられなくなって。まあそれからいろんな小説読んでどうにか生き延びたんだけど、、このままの文学的生活ってんじゃ生きていられないと思って、新聞記者っていういわゆる「雄々しい」実社会に飛び込んだわけ。
――新聞社は男社会ですもんね。特に昔は。
雄々しい社会の中で抗っていった。その時にカウンターの技術を覚えたんだよね。対抗することを、ね。それはその時の自分には絶対に必要なことだったと今でも思う。(ハードボイルド小説の探偵)フィリップ・マーロウじゃないけど、「タフでなければ生きていけない。優しくなれなければ生きている資格がない」って。その2つを獲得するために新聞記者になることが必要だったんですよ。
――北丸さんはそうやって闘ってきたんですね。僕や、もっと若い世代には、どうやって闘っていいか分からず苦しんでいる人も多いと思います。そういう人たちにアドバイスは?
アドバイスはないよ。今の若い世代とぼくらの若い頃とでは、置かれている状況が違う。私の世代は私の世代で闘ってきたし、その延長線上で闘っていくことしか知らない。それはおれの闘い。だから教えられることはないんだ。ただね、こちらから情報は提供できる。その情報をもとに君たちが何をするのか、それは君らの問題。おれはおれ以外の闘いは出来ないのよ。
吉本隆明の『小さな群への挨拶』という詩に、こんなフレーズがある。
ぼくはでてゆく
冬の圧力の真むこうへ
ひとりっきりで耐えられないから
たくさんのひとと手をつなぐというのは嘘だから
ひとりっきりで抗争できないから
たくさんのひとと手をつなぐというのは卑怯だから
1人じゃ闘えないから他の人と手をつなぐというのは、おれは違うと思ってる。1人で闘える人間だけが他の人と手をつなげるんだ。そういう気概をみんなが持つべきだとは思わない。でも、そういう人間がいてもいいでしょ? 君がそうなるかどうかは、君の決断。アイデンティティって、自分が何であるか、ということと同時に、自分は何でありたいか、何であろうとするのか、という問題でもあるから。

(取材・文:宇田川しい 写真:坪池順 編集:笹川かおり)
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
失われた主語を取り戻すために、抵抗する。 北丸雄二さんが語る『愛と差別と友情とLGBTQ+』