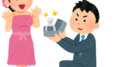ここ数年で、あらためて社会的な課題として認識されるようになった「性教育」に、10年前から取り組んできた男子校があります。立教池袋中学校・高等学校です。
教員も含め、学内の9割が男性という環境で、性教育プロジェクトを発案したのは、養護教諭の真崎昌子さん。そのきっかけのひとつは、学内で耳にした「ホモ」というワードでした。

生徒たちに、性について正しく知識をつけ、自分と他人を尊重しながら人生を歩んでいってほしい。そう願ってはじまった性教育が根付くまでには、さまざまな紆余曲折がありました。
学校での性教育、もっとも大きな関門
――なぜ性教育に取り組もうと考えたのですか?
性教育について意識しはじめたきっかけのひとつは、学校内で耳にした「ホモ」というワードでした。私が本校に勤務し始めた2004年頃、保健室で仲のいい子同士が近い距離でしゃべっていると、誰かが「ホモ」と声をかけるのを目にしたのです。
「ホモ」はそもそも差別的な用語ですし、その言葉を投げかけられた側は傷つき、友達と気軽に仲良くできなくなってしまうでしょう。また、女子は初潮が来る時期に思春期の体の変化について学ぶ機会が設けられている一方、男子はそうした機会が少なく、自分の成長をうまく受け入れられないことが多いことも知りました。
そこで、性や命について正しい知識を学ぶことで、ありのままの自分と他者を受け入れ、多様性の理解のもと、自ら考えて自分の人生を生きてほしいとの思いから、性教育に取り組み始めました。
――実際に性教育が始まったのはいつですか?
2011年、中3に向けて助産師さんに命と思春期の性について講義してもらったのが最初です。本校は私立学校で、教員たちが「生徒のために」とさまざまな取り組みを行っているため、同様の理由で新しい取り組みが受け入れられやすい風土があるのです。
2013年には、高1に向けて泌尿器科医の岩室紳也先生に「思春期の性とエイズ」という講演をしてもらいました。企画の段階では躊躇する先生もいて、校内でどう受け止められるか内心ドキドキしていましたが、講演後は「本校の生徒全員に聞いてほしい話だった」という声も上がるほどでした。
そこで2014年、次のステップとして生徒たちの性に関する知識や意識の実態に合わせた性教育を実施したいと考え、アンケートを企画しました。しかし、実施の是非について教員の間でも議論が巻き起こり、企画は断念することに。反対意見の中には、アンケートに出てくる性的な単語を見た教員からは「寝た子を起こす」という不安の声もありました。
――「寝た子を起こす」とは、性教育に取り組む人たちがたびたび投げかけられる反対意見です。どうやって、その状況を打破できたのですか?
同時期に、保健室の資料棚から「本校の性教育」という保護者向けの124ページからなる報告書が出てきたのです。本校の前身である立教中学校では1950年代から性教育に取り組んでいたそうで、これは1970年代の資料でした。
アンケートに反対していた生徒部長の先生に資料を読んでもらい、あらためて性教育の必要性について話をしました。すると、その先生も意義を理解し、「まずは教職員に対する啓発が必要だ」と、性教育の研究・研修を担当するプロジェクトチームの立ち上げに力を注いでくださったのです。
――プロジェクトはどのように進んでいったのでしょうか。
初めに、現在の立教中高での性教育、また一般的な教科教育での性教育についてリサーチしました。同時に、「性教育とは単に性や性交渉について教えるものではなく、自分を肯定し、相手を肯定しながら人生を歩むためのものである」とあらためて定義したうえで、教職員に研修を実施しました。
――まずは先生の啓発から始められたんですね。
性教育を進めるうえで、教職員への啓発活動は必須でした。他校の養護教諭からは、性教育に関する教職員の理解と共通認識を得ることの難しさが、性教育を進める上での障壁となるともよく聞きます。
他にも、教職員が生徒への性教育の講演に同席したり、生徒の感想から彼らの性教育の受け止め方を知ったりしたことで、少しずつ性教育への理解が深まり、共通認識が広まっていったと考えています。

2017年には、性教育を研究し、中高の6年間にわたる性教育を構築していくため、プロジェクトチームが「性教育研究委員会」という委員会活動に発展しました。私は委員長に任命されましたが、チームのメンバーとともに試行錯誤してきたおかげで、ゆっくりと、しかし着実に性教育が根付いていきました。
――委員会活動では、どのような取り組みをしたのでしょうか。
まず、本校の性教育の目標を決め、毎年配布する学生生活の手引き書「スクールハンドブック」に掲載しました。また、学年ごとのテーマや講義、講演の回数、立て付けなどを議論していきました。

1970年代に性教育を担当していた体育科の先生ともお話しました。全教科を通して性教育研究事業を行うほどの熱心さで、当時NHKの番組にも取り上げられたそうです。
ヨーロッパでは性教育は人権教育の一環とされ、「寝た子を起こすのではなく、寝ているうちに教えてしまう」といわれており、その実態を学ぶために海外研修もしたそうです。
ただ、当時も性教育は一部の教員に任されるという現実があり、それゆえ性教育ブームの衰退とともに体育や理科の教科内で教える内容にとどまってしまったそうです。
その先生からは、「性教育を人権教育としてとらえること、学年ごとにテーマを持って進めること、委員会で良いと思ったことを修正を加えながら進めることが大切だ」とのアドバイスもいただきました。
先生のお話を聞き、委員会では、たとえ熱心な教員がいなくなったとしても衰退しないよう、継続可能な性教育を根付かせていこうと話し合いました。
生徒に向けて専門家が真摯に性を語る意味
――2018年には、中1から高3まで各学年で講師を招いた性教育プログラムが始まりました。具体的にはどんなものですか?
中2、高2は年2回、それ以外の学年は年に1回、各学年に設定したテーマにそって、外部の専門家を招いた講義・講演を行っています。保護者に本校の性教育を理解してもらうため、「性教育・人権教育だより」の配布も始めました。

2020年度からは、ハラスメント予防のため、性教育とあわせて人権意識を高める教育も推進していくことになりました。いじめも含むハラスメントの防止に取り組むため、スクールハンドブックに「すべての人びとの人権が尊重される学校生活のために」という文書を載せ、入学時にはそれに沿った授業をしています。この文書は、年度初めに行われる全教職員会議でも共有しています。


――性教育プログラムのあとに感想を集め、無記名の感想集として配布しているそうですね。どんな声が届くのでしょうか。
毎年実施している中3を対象にした「『せい』の教育」では、妊娠の仕組み、妊娠時期の女性の変化も丁寧に扱ったうえで、出産の場面を見せていますが、生徒からは命の尊さや親への感謝、性交渉に対する意識の変化などが素直な言葉で綴られます。

高1の「思春期の性・エイズ」では、実際にHIV感染者の治療にあたる岩室紳也先生から話を聞くことで、「性について自分ごととして考えられるようになった」という意見が多く上がりました。
「自分の周りでは性やHIVについて話してくれる人はいなかった。しかし、他人事のように聞き流していたHIVが自分の身近な問題になるかもしれないことに驚いた」という声や、「もし付き合う人ができたら、相手が生理のとき、セックスをするときに常に相手を気にかけられるカッコイイ男になりたいと思った」といった声も。
現場を経験している専門家が直接、真摯に話をしてくれることで、性が真剣に語るべきトピックだと伝わるのでしょう。それは、自分の性を肯定的に受け止め、ひいては自分の人生を大切に生きることにつながるのだと信じています。
――性教育プログラムが始まってから4年が経ち、学校の雰囲気に変化はありましたか?
まず、どの学年でも性教育の講演会があることが当たり前になり、私が声をかけるのではなく、担当の先生方から実施時期について相談してくれるようになったことです。教職員が「学校で性を語る」「学校で性を学ぶ」ことが重要だという共通認識を持っているのは、生徒たちに伝わっていると思います。
校内では、生徒たちからの「ホモ」という言葉を聞かなくなりました。高校では、ある生徒が授業中に女性の教員へセクハラめいた言葉をかけたとき、すぐに別の生徒が「それハラスメントだよ」と注意したという話も聞きます。教職員の意識もアップデートされ、生徒たちにも性教育や人権の大切さが伝わり、学校の空気が変わったのも感じます。
日本では、性をはじめとして大人が自信を持って語れないないことについて、子どもたちを遠ざけ、守ろうとする傾向があると感じます。
でも、私たち大人は、もっと子どもたちを信頼していいのではないでしょうか。
大人が真剣に性を語り、子どもの発達段階に合わせて正しい知識を伝えていけば、子どもたちはしっかり受け止め、自分で考えて判断し、歩んでいきます。本校の性教育は、教育目標である「テーマを持って真理を探究する」「共に生きる」の根本を支えるものだと思っています。できることを粛々と続け、性教育プログラムを絶やさないようにしていきたいです。
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
「性教育」が根付いた男子校、その10年間の取り組み