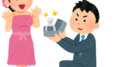リッチランド高校のフットボールチームのトレードマークは、キノコ雲と、原爆投下に使われたB29爆撃機だ
リッチランド高校のフットボールチームのトレードマークは、キノコ雲と、原爆投下に使われたB29爆撃機だ【関連記事】原爆を作った「オッペンハイマー」の苦悩は、被害者より優先されるべきなのか。倫理学者が抱く危機感
高校の校章は、原爆を象徴するキノコ雲。町の通りは「Nuclear(核)」と名付けられ、ある住民はキノコ雲は「わが町の誇りだ」と語るーー。
その町の名は「リッチランド」。1945年に長崎に投下された原爆の材料であるプルトニウムの生産拠点となったアメリカ・ワシントン州の核施設「ハンフォード・サイト」で働く人と、その家族が住むために作られたベッドタウンだ。
その町で暮らす人々に話を聞いたドキュメンタリー映画「リッチランド」が、7月6日から日本で公開されている。
クリストファー・ノーラン監督の「オッペンハイマー」が、原爆開発を率いた科学者や軍人中心の映画だとするならば、本作は「オッペンハイマー」以降の、核兵器が存在する世界で生きる市民たちを描いたドキュメンタリーだ。
アメリカでは不可視化されている、核開発により引き起こされた放射線被ばくによる健康被害に光を当てるとともに、暴力の歴史を背負う町で生きる人々の複雑な感情を浮き彫りにし、その背景にある保守的思想と「愛国心」の関係にまで迫った。アイリーン・ルスティック監督に話を聞いた。
「どんな人も尊厳を損なうことなく表象したい」
ハンフォードは、アメリカが第2次世界大戦中に原爆を開発した「マンハッタン計画」の拠点の一つ。古くからワナパム族など6つの先住民族の居住地だったが、核施設建設のために、土地を強制的に奪われた。
原爆の材料となるプルトニウムが生産され、終戦後も、旧ソ連との冷戦を背景に核兵器の開発は加速した。1987年に施設の稼働が停止したが、今も放射性廃棄物が貯蔵され、周辺には、放射性物質による深刻な健康被害や環境汚染が残っている。
リッチランドは原子力産業によって発展し、現在も住民の多くがハンフォードの浄化にかかわる仕事をしている。
原爆という多くの犠牲者を生んだ大量破壊兵器を生産した歴史を背負う町にもかかわらず、映画の序盤に登場する住民たちは「キノコ雲は殺しのシンボルじゃない。この町の業績だ」「この町は社会実験とも言える。しかも成功に終わった例」と、誇らしげに話す。
ルスティック監督はインタビューで本作について「この町を批判したくて撮ったわけではない」とし、こう続けた。
「核兵器を生んだ歴史を誇る人々の語りは、この町の自画像そのものと言えるでしょう。しかし、だんだんと進むにつれ、この町の矛盾や複雑さ、実際に放射能汚染による健康被害があったことが炙り出されていきます。
 アイリーン・ルスティック監督
アイリーン・ルスティック監督このような構成にしたのは、リッチランドがどういう町なのかを深く知ってもらうため、観客を誘導していく必要があったから。そして、『原爆投下により戦争が終わった』『我々は偉大な貢献をした』と信じる、リッチランドの人々にも観てもらいたかったからです」
監督の言葉通り、作品が進むにつれ、核兵器の開発により居住地や信仰の拠り所を奪われた先住民、健康被害を訴える住民、広島の被ばく者の子孫、そしてキノコ雲の校章に反対するリッチランド高校の学生たちが出てくる。
それと同時に、原爆を「町の功績」だと肯定する人々を糾弾するような撮り方も決してしない。誰に対しても平等にカメラを向けたのは、なぜだろうか。
「私が何よりも重要視したのは『傾聴』であり、どんな人に対しても尊厳を損なうことなく表象したいと思いました。この映画の目的は、自らの国の暴力の歴史、痛みを伴う歴史に、人々はどう向き合い、受け入れ、ともに生きていくのかを思考するために、すべての人々の物語を傾聴し、それをシェアしていくという、一種の政治的な実践です」
 リッチランド高校の学生たちは、キノコ雲の校章に疑問を持ち話し合う
リッチランド高校の学生たちは、キノコ雲の校章に疑問を持ち話し合う「豊かな暮らし」と引き換えに差し出してきた、命や健康
原爆の開発が始まる前、リッチランド周辺はコロンビア川が流れる小さな農業の町だった。しかし今、ある住民は自然の美しさや住みやすさを強調する一方で、「川の魚は食べない」と言う。
ハンフォードの核施設から放出された放射能を原因とした健康被害を訴える人は後を絶たず、リッチランドの一角には、幼くして亡くなった子どもたちの墓石が並ぶ。
本作の後半には、核施設の作業員だった父親が、放射線被ばくの影響で59歳で亡くなったというキャロリンさんが登場する。「もっと稼ぎたいやつはいないか?」と誘われた父は、「家族を養うために」と健康リスクがより高いとされる原子炉の掃除の仕事にも就くようになったという。キャロリンさんはカメラの前で涙を流しながら、こう話す。
「亡くなる1カ月ほど前に、『信じる相手を間違えた』と父は言ってた。認めるのはとてもつらかったと思う。仕事のグチひとつ言わなかった人。それに、悪いことなんて言えない。日々の糧があるのも、家や衣服があるのも仕事のおかげ。私も大学に行けた」
キャロリンさんの語りは、「豊かな暮らし」と引き換えに、住民たちが健康や命を差し出す選択を迫られてきた実態を突きつける。
その一方で、ルスティック監督によると、いくら健康被害の問題が表面化しても、リッチランドで核兵器を表立って批判する人は今でも決して多くないという。
「彼女の話は感動的に映るかもしれませんが、その前提にあるリッチランドの成り立ちや、住民たちがなぜ健康被害のリスクを負ってまでこの町に残り続けるのかを知らなければ、その悲しみの深さを理解することはできません。
被害を受けた人たちの物語や言説は、リッチランドや原爆を誇りに思う人たちにとっては、抵抗感があり、目を背けたいものです。これはリッチランドだけの問題ではなく、人間の本質的な部分だと思います。
裏を返せば、保守的なコミュニティの中で、自分たちの成功に水を差すような言説や映像、イメージは許されていないということでしょう。リッチランド周辺の、博物館などの公的な歴史教育の場では、日本の原爆投下後の映像やイメージはありません。記録として世の中にはあるけれど、この町にはないのです。
映画『オッペンハイマー』でも、原爆投下後の広島や長崎の描写はありませんでしたが、そこには、アメリカのメンツや、核への肯定的な認識を脅かすものは封印していく傾向を見てとれると思います」
 ハンフォード・サイトを見学する人々
ハンフォード・サイトを見学する人々キャロリンさんのように、本作で被害の実態や核兵器について「感情」の面から語るのは女性が多い。本作のスタッフは全員が女性で、「フェミニストフィルムメーカー」を名乗るルスティック監督にとって、それは意図的なことだったのだろうか。
「核問題にかかわる感情、つまり、この暴力の歴史を背負った町で暮らすのはどういう気持ちなのかという感情の部分を映画に取り込みたいと思っていました。けれど、話を聞いても、核にかかわる技術者や科学者は圧倒的に男性が多く、プルトニウムの作り方や町の歴史の話はしてくれても、感情については口が重たく、無関心だとすら感じました。そういう感情について自分の言葉を持っている人は女性に多かったのです。核兵器に関する映画を作っているとしても、フェミニストである私の視点は出ていると思います」
批判の対象にされてきたリッチランド
ルスティック監督が初めてリッチランドを訪れたのは2015年。町のあらゆる場所でキノコ雲がシンボルとなっている状況に疑問を持ったという。その後4年半かけて通い、撮影を行った。
これまで、チェルノブイリやスリーマイル島の原発事故などを受けて反核の機運が高まるたびに、リッチランドは国内外のジャーナリストやアクティビストからの「批判の対象」になってきたという。
そうした背景もあり、外からやってきた「部外者」への警戒心は強かった。それでもルスティック監督は住民たちの話に丹念に耳を傾け続けた。
「リッチランドでは、自分たちが悪く言われることへの抗議の気持ちや、警戒心、反動が非常に強く、批判に対して被害者の意識を持ってしまっています。自分たちの仕事に価値があるのだと認められたい、歴史上の自分たちの軍事的な貢献や『国を守った』という言葉を信じ、気分よくいたいという心情があるのでしょう。私はそれに反論するのではなく、理解したいと思ったのです」
撮影を進める中で、リッチランドの住民たちが感じる誇りや、原子力産業批判への反発心には、「愛国心」が深く結びついていると考えるようにもなった。
「自分たちを強く見せる」ための愛国心
ルスティック監督が「愛国心」に関心を持ったのは、ルーマニアから亡命した両親のもとでイギリスで育ち、現在はアメリカで暮らす移民一世である自身のルーツも関係しているという。
「私自身は愛国主義的な感覚がわからず、だからこそ考え続けてきました。どうやら、愛国心とは、人や国を動かすほどに大変に大きな影響力があり、時に理性さえ失わせるもののようです。自分の国を愛することで、何かが見えなくなってしまっているのに、人々はなぜこれにとらわれ続けているのでしょうか」
 ケネディ大統領は1963年にリッチランドを訪問し、地元の人らを称えるスピーチを行った
ケネディ大統領は1963年にリッチランドを訪問し、地元の人らを称えるスピーチを行った本作では、1963年にリッチランドを訪問したケネディ大統領が、原子炉の竣工を祝い、「ここで働いている人たちがアメリカを強く保った」と称賛するスピーチ映像も挿入されている。ルスティック監督によると、ケネディ大統領はリッチランドを訪れた唯一の大統領で、以降は誰も足を運んでいないという。
「自分たちは先祖の時代からこれだけ身を尽くして犠牲を費やして、核兵器を作り戦争を終わらせた。にもかかわらず、今や国から忘れられ、見えない存在にさせられ、それどころか批判の対象にさえなっているーーそうした感覚が、リッチランドには根強くあるのだと思います。
キノコ雲の校章に反対したリッチランド高校の元教師は、同僚たちから『裏切りであり、反リッチランドで反米』だと凄まじい反発を受けたと話していました。つまり、原爆を生んだ歴史を肯定する気持ちと、国を愛する気持ちが結びついているのです。
同時に、これはリッチランドだけの問題ではないことも強調しなければいけません。自分たちを苦しめるとわかりきっている国の政策であっても、国家的なナラティブに愛着を持ち、それを内面化してしまっている。自ら愛国主義を身にまとい、自分たちを強く見せて、その言説を繰り返し増幅させていくという傾向は、2017年にトランプ前大統領が就任した頃から、白人労働者階級の人々を中心にアメリカ全土で見られます」
「アートは未解決で複雑な感情を抱え込むことができる」
本作では、アメリカの原爆投下や原子力産業に対するわかりやすい「答え」は示されない。ルスティック監督が目指したのは、映画を通じて「居心地の悪い、アンビバレントな空間」を作ることだったという。
リッチランドの住民たちの語りが、核兵器の賛否や善悪という二項対立に収束することに抗うために作品に取り入れたのは、インスタレーションや合唱などのアートだった。本作のメインビジュアルには、広島出身でアメリカ在住の被ばく3世のアーティスト、川野ゆきよさんの原爆を模した立体作品「(折りたたむ)ファットマン」が起用されている。祖母の着物をほどいた布を、川野さん自身の髪で縫って作ったものだ。
 川野ゆきよさんの「(折りたたむ)ファットマン」
川野ゆきよさんの「(折りたたむ)ファットマン」映画の最後を締めくくるのも、この川野さんのアート作品だ。ルスティック監督は、その狙いをこう話した。
「アートは、すべてを語り尽くすことはできないけれど、言葉を超えて、未解決で複雑な感情をまるっきり抱え込んで、ありのままに保持することができると私は考えています。
先ほど、撮影では『傾聴』の姿勢を重んじたと話しましたが、現代は、語るだけで聴かない時代に入ってしまったと思います。心豊かに人の話に耳を寄せる、他者の人間性を理解するために傾聴するという態度が、割に合わないと感じる人が多いのかもしれません。確かに、実生活において傾聴することは決して簡単なことではありませんし、暴力や差別の話題になるとなおさら困難です。けれど、アートは、立場や考え方の異なる人たちを同じ場所に招き入れ、傾聴の空間を開くことができる数少ない方法だと思います」
(取材・文=若田悠希/ハフポスト日本版)
▽作品情報
『リッチランド』
7月6日(土)より、シアター・イメージフォーラムほかにて全国順次公開
監督:アイリーン・ルスティック
製作:コムソモール・フィルムズ
配給:ノンデライコ
©2023 KOMSOMOL FILMS LLC
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
「キノコ雲が誇り」の町が背負う、矛盾と痛み。「オッペンハイマー」以降の世界で、暴力の歴史とどう生きるのか