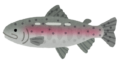「ユニクロ」などを運営するファーストリテイリングと国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は11月9日、バングラデシュの難民キャンプで生理用の布ナプキンを生産・配布する活動への支援を始めたと発表した。
なぜ布ナプキンでの支援を行うのか。UNHCRバングラデシュ・ダッカ事務所上席開発担当官の長谷川のどかさん、ファストリ社サステナビリティ部リーダーの伊藤貴子さんらは、記者会見で3つの理由を話した。
難民キャンプの75%は女性と子ども
支援先であるバングラデシュ南東部のコックスバザールは、ミャンマーとの国境そばに位置している。ロヒンギャ難民およそ94万人以上が滞在しており、その75%が女性や子ども。男性は武力衝突や暴力などで命を落としたり、戦闘要員として元の住処に残っていたりする場合も多いからだという。
暮らしにはさまざまな物資が必要だが、生理用品を必要とする人も多く、皆に行き渡らせるために安定的な供給が必要だったという事情がある。
 現地で生産する布ナプキンについて紹介するUNHCRバングラデシュダッカ事務所上級開発担当官の長谷川のどかさん
現地で生産する布ナプキンについて紹介するUNHCRバングラデシュダッカ事務所上級開発担当官の長谷川のどかさんそして、女性が報酬を得る手段も必要だ。2017年のロヒンギャ危機から5年が経ち、滞在は長期化している。難民キャンプでは人道支援の配給に頼って生活しているが、世界中で難民が増え続ける状況に、来年のUNHCRの予算はさらに減少するなど厳しい状況にある。
保守的な価値観が社会の主流で「女性に教育などいらない」「女性は家の中にいるべき」という家庭で育った女性たちも多い。しかし、今は女性がひとりで家計を支えている家族も3割ほどある。常識を覆してでも、今後の家族の生活を支え、生き抜いていくための手段を身につけなくてはいけない。
そのため、布ナプキンを配布するだけでなく、縫製のトレーニングを行うことで生産にも関わってもらい、将来のスキルの獲得にもつなげるプロジェクトとなったという。
紙ナプキンは「高級品」
アジアの最貧国といわれるバングラデシュの生活水準では、難民ではない一般の人々も含めて紙ナプキンはまだ「高級品」だという。多くの人は繰り返し使える布ナプキンのようなもの、難民キャンプではそれ以下のボロ布を使用することが多く、衛生面でも課題が大きかったと長谷川さんは語る。
1人あたりに配布されるのは7〜8枚。布ナプキンの配布とともに、衛生環境の向上と、生理についての教育も行うという。
 難民キャンプの様子
難民キャンプの様子「服屋として何ができるか」
ファストリ社の柳井正会長は、記者会見でこの支援にあたり「服屋として何ができるか」を考えたと語る。バングラデシュ国内には、ファストリ社の生産パートナーとなっている企業の工場もあり、縫製技術の指導での支援も得ているという。
「専門技術や知見をもつ企業と取り組みを進められ、色々な面で学ばせてもらっている」と長谷川さん。例えば、現場で布ナプキンの形状を見て、どんなミシンが必要かなどの知識の共有がファストリ側からあったという。
また、布ナプキンは洗って使うことができるが、現状のものは湿度の高い環境の中で乾かしにくいなど、まだまだ改良の余地があると伊藤さん。「アパレル企業として、これまで考えてきた生産効率の向上や、快適に使える質の向上を目指すことで貢献していきたい」と話した。
 記者会見で現地の様子や必要な支援について話すファストリ社の伊藤貴子さん(左)とUNHCRの長谷川のどかさん
記者会見で現地の様子や必要な支援について話すファストリ社の伊藤貴子さん(左)とUNHCRの長谷川のどかさんオリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
なぜ、布ナプキン生産で難民を支援するのか?ファストリ、UNHCRが語った3つの理由