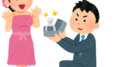2021年10月に刊行された『嚙みあわない会話と、ある過去について』(講談社文庫)は、作家・辻村深月による短編集だ。「嚙みあわない会話」――すなわち、相手が思いもよらぬことを唐突に語りだし(少なくともこちら側にとってはそう感じられて)、コミュニケーションの文脈を共有できない状況。振り返ってみると、思い当たる場面は多々ある。
例えば、私の場合。過去に勤めていた会社を辞め、別の会社に転職を決めたときのことだ。自分の意思は、きちんとした手順を踏んで勤務先に伝え、承諾されたはずだった。だが、面談中に上司が突然「でもそんな業界、落ち目だよね」と言い出した。今さら引き留めるわけでもない。最後に何か言ってやりたいとでもいうような、明らかに棘のある口調。「そんな業界」というのは出版業界のことで、確かにそういう見方もできる。ただ勤め先は、転職後も仕事で一緒になる可能性が高い業種だった。シンプルな悪口を、なぜ今? コーヒーをすすりながら、訳が分からなくて背筋が寒かった。心臓の音が大きく感じられたのを覚えている。
あるいは、大学時代からの女友達と久しぶりに会ったときのこと。彼女は母親だが、私はそうではない。彼女が「子どもはまだなのか」と聞くので、私は説明した。「子どもはいないが、夫婦で楽しくやっている。今後もつくるつもりはない」。そんな趣旨のことを、自分なりに丁寧に伝えたつもりだ。夫婦2人で暮らす中で起きたささやかで愛すべき出来事を、その後もさまざま、語ったはずだ。しかし、別れ際。彼女は「次に会うときは、子どもできてるといいね」とほほ笑んだ。まるで「あなたはまだ幸せじゃないよね」と確かめるように。私の話を、聞いていなかったのだろうか? これも正直、面食らった。悲しいとか不快だとかいうより、「怖い」と直感した。
「嚙みあわない会話」は、ホラーだ。何かの事柄をめぐって意見が対立しているときよりよほど、心臓がドキドキする。相手が何を言っているのか分からない。どうしてそんな言動をするのかが分からない。「分からない」は恐怖だ。
この短編集には、そういう種類の「ホラー」4篇が収録されている。どの話の登場人物も、目の前に「話が嚙みあわない」人物が現れることをきっかけに、他者の心の内に触れ、自身が見ていた世界のあり方までもが変わってしまう。
特に印象的だった『パッとしない子』は、例えばこんな話だ。
主人公は、小学校教諭の松尾美穂。国民的アイドルとして人気を博している高輪佑をかつて教えたことがあり、周囲から「どんな生徒だったの?」と興味本位で聞かれることも多い。「目立ってたのはもっと別の子たちだった」。実際、美穂が担任していたのは佑の弟で、佑自身を教えたのは担当科目の授業のみ。特に記憶に残る生徒でもなかった。美穂は誰かに聞かれるたび、率直にその印象を語ってきた。そんなある日、テレビ番組の企画で佑が母校を訪れ、2人は再会する。
懐かしい、ちょっとだけ先生と2人で話してもいいですか――。佑から爽やかな笑顔で声をかけられる美穂。美穂自身も読者も、そこで美しい思い出や感謝の気持ちが語られるのだろうと想像する。
だが瞬間、彼の口を突いて出るのは思いもよらぬ一言だ。
「先生、ぼくのことを、当時はパッとしない子だったって、あちこちで言っているって本当ですか?」
美穂は「そんなつもりではなかった」。弁解しようとするが、嚙みあわない。その言葉はもはや、届かない。
佑は冷ややかに追及する。在学当時、美穂は生徒の間で人気の若手教師で、調子に乗っているように見えたこと。その美穂が、友達の悪口を言う生徒をたしなめなかったことで、仲間外れにしてもいいという教室の雰囲気が加速したこと。クラスの中心にいる「強い」生徒とばかり仲よくして、佑やその弟のような目立たない生徒には、いかにも疎ましそうな態度で接していたこと……。自分が美穂を憎む理由を列挙し、徹底的に攻撃する。
記憶にない、と美穂は呆然とする。だが同時にこうも思う。問題は、佑が「美穂がそう言ったと思っている」こと、そう記憶しているということだ、と。
この「ホラー」は、何を意味しているのか。文庫版刊行にあたって寄せられた、臨床心理士の東畑開人さんの解説が示唆に富む。
東畑さんによれば、嚙みあわない会話が立ち上がるのは、そこに「幽霊」がいるからだ。幽霊とは、「非業の死を遂げた心」から生まれる。
「『なんでわかってくれないの?』とは言えない。それはわかってくれる可能性がない人に対しては発することができない言葉なのだ。相手が変化することを期待できないならば、自分を変化させるしかない。やり方はシンプルだ。『こういう人なのだ』『どうしようもないのだ』と思って、心を殺す。すると、心は非業の死を遂げる。(中略)このようにして嚙みあわなかった過去は凍結され、私たちはその後の人生、幽霊を抱えて生きざるをえなくなる」(東畑さんの解説より)
つまり佑は、何も言わなかった。何も聞かれなかった。黙って心を殺し、その幽霊を抱え続けて生きてきた。
幽霊という比喩は実に秀逸だ。私たちが幽霊を恐ろしいと感じるのは、その相手と会話が成立する可能性が断たれていると感じるからだと思う。「私はこんな事情で深く傷つきました。あなたにこういう形で手を貸してもらえたら、少し楽になります」――仮にジャパニーズホラーの幽霊と出くわしても、こんなふうに理路整然と話されたら、私たちはそれほど戦慄しないだろう。相手が井戸から這い出てきても、後ずさりをするどころか心配するのではないか。
幽霊は何が欲しいわけでもない。謝ってほしいわけでもない。会話ができない。ただ「私の心は聞かれなかった」という存在理由だけを主張してくるから、幽霊は怖い。
物語を反芻するうち、日頃は胸の奥底にしまっておいたような「心を殺した」経験が、幾つも幾つも思い出されてくる。同時に、自分が何気なく、悪気なく、誰かの心を殺したこともあったのではないかと考え込んでしまう。また心臓の音がうるさくなる。東畑さんが書く通り、誰もが幽霊を抱えて生きていることを、本書は思い出させてくれる。
ひょっとしたら、冒頭で回想した元上司や女友達も、幽霊を抱えていたのだろうか。
たしか十数年以上のあいだ、同じ会社で働き続けていると言っていた上司。そのキャリアを否定されるようなことを、誰かに言われた経験があったのかもしれない。
私のことを「子どもがいないから幸せではない」と扱いたがった友人。その日、見慣れない紺色のワンピースを着ていた。かつては派手な服装が好きだったけれど「子どもの受験の面接対策塾の帰りなの」と笑っていた。子育てに関わる悩みも話していた。「私の人生のほうが正しいよ」と念を押したくなるような傷つきを、彼女も抱えていた可能性を想像してみるのは、行き過ぎだろうか。
幽霊が生まれると、取り返しがつかないことのほうがおそらく多い。カウンセラーなどの専門家、親密な関係にある家族や友人との間では、一度死んだ心の蘇生を試みるケースもあるだろうが、難儀であることには間違いない。赤の他人であれば、なおさらだ。だから本書を絶望の物語として読むことはできる。
けれど、これらのホラーは「聞かれたかった心が確かに存在した」ということを示してもいる。ちなみに単行本として刊行されたのは2018年6月である。
自分の言葉を受け取る人がどんな顔をしているのか、どんな状況にいるのか。コロナ禍で人と人との距離が遠のいて、とても見えづらくなった。「心がある」という当たり前の事実が、見過ごされやすくなっている気がする。本書をきっかけに、他者の心に思いを馳せる時間を、持ってみてはどうだろうか。
(文:加藤藍子@aikowork521 編集:若田悠希@yukiwkt)
オリジナルサイトで読む : ハフィントンポスト
「嚙みあわない会話」はなぜ生まれるの? 心に住む「幽霊」を描いた、作家・辻村深月の物語