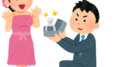コロナ禍で開催された東京オリンピック・パラリンピックが終了した。
スケートボードやサーフィンといった新種目の登場で、勝ち負けだけに汲々とせず楽しむというスポーツの本質を私たちに訴えてくれた大会だった。
その一方、ニューヨーク・タイムズ電子版が大会期間中、「世界2位でも謝る」という見出しで報じ、金メダル以外の結果となった日本選手の振る舞いが取り沙汰された。
柔道混合団体で銀メダルを獲得した向翔一郎選手が「チームのみんなに申し訳ない気持ちがある」と謝れば、レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級で同じく銀メダルの文田健一郎選手は「不甲斐ない結果に終わってしまい申し訳ない」と涙を流した。
大会運営のボランティアや指導者、家族に「勝って恩返ししたかった」とも語ったが、周囲の人たちは金メダルでないと許せないなどと思っていないだろう。


前回リオ五輪でも、銀メダルだった女子レスリング吉田沙保里さんが号泣しながら謝った。だが、「2位でごめんなさい」とシリアスに謝る海外選手を見た記憶はない。これは日本人独特の慣習なのだろうか。

「負け」の受け止め方
学校の部活動などで暴力や暴言が今もはびこる実態を調査し、報告書「数え切れないほど叩かれて」を昨年発表した国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ(HRW)の代表を務めるミンキー・ウォーデン氏にこのことを問うと、こう答えてくれた。
「エリートレベルにいる全てのアスリートは皆、勝ちたいと思っている。ただし、日本以外で、金メダル未満の勝利に対して謝る必要があると感じているアスリートは極めて少ないでしょう。彼らはスポーツでの負けは成長の過程であり、スポーツでは誰かが負けることになるということを理解しています」
またウォーデン氏は、元女子サッカー米国代表の五輪金メダリストで国際スポーツ人権センター最高経営責任者(CEO)のメアリー・ハーベイ氏からこんな話を聞いている。
「勝利から人生の教訓を学んだことは無いけれど、試合に負けたときはレジリエンスや覚悟することを学んだわ」
海外と日本の選手では、なぜこうも「負け」の受け止め方が違うのだろうか。
謝る選手を見ていて、辛かった
そこで、2位を否定された経験のある学生に話を聞いてみた。
2017年に県大会で2位になったハンドボール強豪高校の監督が、大会直後に選手の前で2位の表彰状を破って問題になった。そのとき賞状を破られた側の生徒だった酒巻慶治さん(21)にも、オリンピック選手の“謝罪”について尋ねてみた。
「テレビで謝罪している選手を見ていて辛かったです。悔しいのはわかるけど、何も謝らなくても…」
当時、酒巻さんたちが県大会決勝で敗れ、高校の連勝記録はストップ。会場の隅でミーティング中に生徒たちの目の前で、顧問教諭によって賞状は真っ二つに破られた。

「いや、賞状破っていいのか?と、率直に思いました。ずっと勝っていた高校なので、2位じゃ監督は認められないのだろうなと想像しました。僕らは優勝を目指していたチームです。それぞれの学校で目標は違うかもしれないけれど、2位をあんなふうに否定しちゃうと、じゃあ3位以下のチームはどうなるんだよってなりますよね。他のチームに何も配慮がないなあって残念でした」
3年生が引退し新チームになったばかりの新人大会。2年生だった酒巻さん自身は「チームはまだまとまっていなかったし、負けたのは仕方がないと思っていた」。
3年になってからの大会は王座を奪還した。

スポーツ文化、日米の違い
酒巻さんは大学2年時にアメリカに留学した際、日本と異なるスポーツ文化に触れた。
「バスケットやアメフトで自分たちの大学チームを、みんな熱狂的に応援するんです。しかも、試合を観に行って自分たちの大学が負けても、どの学生も文句を言いません。ああ、楽しかった、また次だねと言って帰っていく。日本人は応援しているチームが負けると怒ったりしますよね。もちろんプロとかだとそうなるのかもしれませんが、NBA(アメリカのプロバスケリーグ)でさえそうじゃなかった」

NBAのチーム関係者によるこんなSNSの投稿が、ファンによって拡散されていた。「試合には負けたけれど、みんな選手をリスペクトしてくれ!」
こうした光景と、2位の賞状を指導者に目の前で破られた経験を比較して、酒巻さんは「日本のスポーツ文化は遅れてるんだ」と感じた。
現在大学4年生。就職活動などで企業側に「体育会の学生は(企業の人材として)魅力がある」と言われた。スポーツをやっている人間は「社会に出てもチームの一員として協力できると考えられている」。
酒巻さんがそう感じたように、スポーツは貴重な成長コンテンツだ。ただし、そうなれるのは、選手主体で取り組める環境であれば、の話だろう。選手が自分で考え、模索する機会を与えず、ああしろこうしろと指示・命令してしまう指導者はいまだ一定数存在する。
「コーチの言う通りやるだけでは、人として成長できない気がします。日本は、選手も、コーチも、保護者も、勝利至上主義の人が多いですよね。勝つことがすべてというか。選手も周りの目を気にするようになってしまう。だから、負けると謝っちゃうのかも。謝られた人も困っているんじゃないでしょうか。スポーツの本質を分かっている人は、ベストを尽くしたのならいいじゃんって思うはずです」

「応援したのに負けやがって」
筆者は数年前、甲子園に出場した首都圏の高校が初戦負けしたら、寄付をした市民から「金返せ」「応援したのに負けやがって」と抗議の電話が殺到したという話をその学校の教員から聞いたことがある。教員たちは電話口で「すみません」とひたすら謝ったそうだ。
その教員は「選手だってわざと負けたわけじゃないし、ましてはプロでもない。高校生のスポーツが人々にとって単なる娯楽になっていると感じ、悲しかった」とうなだれていた。

コーチや保護者といった身近な関係者だけでなく、日本の社会全体に「勝たないといけない」という空気感がはびこっている。例えば、菅総理がSNSで金メダル獲得者だけに祝いの言葉を伝えたことも、そうした空気感を醸成すると言えなくもない。
さらにいえば、「謝る」ことに重きを置く文化も関係しているようだ。
前出したHRW代表のウォーデン氏は、長野県の公立小学校で昨年11月、高学年の男子児童が男性講師からの体罰を受けて頭蓋骨骨折の大けがを負った暴力事案を例に挙げ「絶対にありえない教育方法だ」と憤る。
ウォーデン氏が例に挙げた報道によると、元講師は児童の胸を足で踏みつけるなどしたという。きっかけは、けがを負った児童が校庭で遊んでいた別の児童にボールを当てた後に謝らずに抵抗したからと言うが、子どもそれぞれの話を丁寧に聴く必要があったはずだ。謝らせることに固執するうち頭に血が上り、こんなことになったのではないかと想像する。
「勝てない自分が悪い」なぜ生まれるのか
HRWは昨年、スポーツの経験者約800人にインタビューとオンラインアンケートを実施。アンケートに答えた25歳未満の381人のうち、およそ19%が何らかの暴力行為を受けていたと回答。委縮する若者たちの中には「私が言われた通りできないから」「勝てない自分が悪いと思っていた」と自己否定する人もいた。
「随分前に禁止されているはずの体罰が存在し続ける限り、全力を尽くしても一番になれなかったら謝らなければと選手は思ってしまう。この“謝罪文化”は、アスリートのメンタルヘルスにとって大きなマイナス要因と言えるでしょう」(ウォーデン氏)。

選手が負けたときに他者に謝る慣習は、指導者による身体的または言葉による虐待によって抑圧され続けてきた歴史の名残なのかもしれない。
HRWジャパンのスタッフらが著した『スポーツの世界から暴力をなくす30の方法』(合同出版)のなかで、元バレーボール日本代表の益子直美さんがこう書いている。
「今だに橋の上から自殺をする夢をみます。チーム全員で死んで(コーチに)お詫びをとみんなで話すのですが、私だけ飛び降りられない。汗だくになって飛び起きたこともあります」
詫びたり、謝ったりする選手が決して悪いわけじゃない。彼らが結果にかかわらずベストを尽くしたことを誇れるよう、スポーツに関わる人や見る側、私たちの社会が変わらなくてはならないのだ。

Source: ハフィントンポスト
銀メダルなのに謝る日本。県2位の賞状、監督に破られた学生アスリートが思うこと