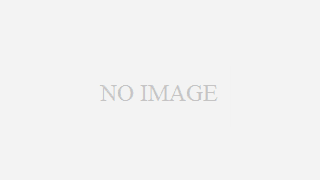東京・新宿にある「プライドハウス東京レガシー」は、毎月第1・3火曜日にトランスジェンダーフラッグに囲まれます。

この日は月に2回開かれている「トランスデー」。
トランスジェンダー当事者のスタッフと話をしたり、ライブラリーに備えられているLGBTQをテーマにした本を読んだり、ゆっくりお茶やコーヒーを飲んだりと、思い思いのスタイルでくつろげます。
トランスデーのことを「楽しみながら人とつながり、安心して過ごせる場所」と話すのは、スタッフのジャンジさん。
そして、トランスデーはトランスジェンダーの人たちだけではなく「誰でもウェルカム」な場所でもあるそうです。
月2回、ここにどんな人たちが集い、どんなつながりが作られるのでしょうか。
【9月】「トランスデー」のご案内❗️
9/7(火)・9/21(火) 13時〜19時まで!
トランスジェンダー当事者も、
そうでない方も、ぜひ遊びに来てください。
ちょっと話したり、本を読んだり、ひと息ついたり…。コロナ対策をしっかりして、
フレンドリーなスタッフがお待ちしています。 pic.twitter.com/aY3nBBVHkX— Pride House Tokyo(プライドハウス東京)🏳️🌈 (@PrideHouseTokyo) August 29, 2021
人と安心してつながれるのが大切だから
トランスデーの日は、ノンバイナリーのジャンジさんのほか、トランスジェンダー女性の時枝穂(ときえだ・みのり)さん、トランスジェンダー男性の浅沼智也(あさぬま・ともや)さん、そしてトランスジェンダーのお子さんがいる小林りょう子さんの4人のスタッフが、訪れる人たちを迎えます。
小林さんは「親同士のつながりも必要だし、子どもにとって一番の応援者となりたい」という思いから、スタッフになったそうです。

このトランスデーの原点は、孤立や孤独を感じているトランスジェンダー当事者のための居場所づくりとして始めた「トランス☆カフェ」というイベントです。
「楽しみながら、つながれる場所を作りたい」と思ったジャンジさんと浅沼さんが2019年に立ち上げ、今でも新宿2丁目で年に1〜2回開かれていますが、トランスデーはより継続的な「定点」として、2021年3月から始まりました。
「定点」を作ろうと思ったのは、トランスジェンダーの人たちが定期的に交流したり、話したり、誰かとつながれる場所が必要だと思ったから。
特にコロナの影響で、直接つながれるリアルな場所が減ったと時枝さんは感じています。
「学校や職場など、生活の身近な場所に、自分と同じようなトランスジェンダーがいないという当事者は少なくありません。そんな人たちにとって、『ここにいけば安心』という場所があるのとないのでは、大きな違いがあります」
「同じような悩みを抱えている人たちとの交流はすごく大事ですし、職場や家や学校以外の、サードプレイスやフォースプレイスを持つことが、セーフティネットになる人もいます」 と、時枝さんは話します。

また、実家暮らしで親にカミングアウトしていない人や、親と良好な関係を築けていないという人たちの中には、家族に見つかるのが心配で、LGBTQ関連の本を買えないという人もいるそうです。
そういう人たちにとって、ライブラリーに備えられている本を読むことも楽しみになっています、と時枝さんは話します。

SNSでのバッシングが傷つけている
安心してつながれる場所がより一層必要となっている理由の一つに、SNSを中心としたトランスジェンダーの人たちへのバッシングの増加があるといいます。
近年、トランスジェンダーの人たちのことがメディアなどで取り上げられ、社会の中で当事者の存在や課題が知られるようになりました。
正しい知識が広がる部分もある一方で、誤った情報をベースにしたトランスジェンダーへのバッシングも起きています。
例えばお茶の水女子大学がトランスジェンダー女性の入学受け入れを発表した時に、男性の著名人が「今から受験勉強をして、入学を目指す」とまるで簡単に性別を変えられるかのような当事者の実態とは異なるツイートをして、バッシングを煽ったことがありました。
他にも、履歴書の性別欄を無くしたり、制服を選択制にする動きが進んだ時に、それに対する中傷や茶化すようなコメント、差別的な書き込みが投稿されることは珍しくありません。
浅沼さんは「『トランスジェンダーはこんな人だ』といった勝手なイメージを作ってバッシングをする人たちがいて、それで傷つく当事者もいるんです」と話します。

SNSに限らず、2021年5月には、自民党の山谷えり子議員が「体は男だけど自分は女だから女子トイレに入れろとか、アメリカなんかでは女子陸上競技に参加してしまってダーッとメダルを取るとか、ばかげたことはいろいろ起きている」と発言したことが報じられ、差別だとして批判を受けました。
こういったバッシングが起きた時に、家族にカミングアウトしていない人や、理解のない家庭で暮らす人の中には、誰にも相談できずに孤立してしまう人もいます。
浅沼さんは「そういう状況で、更に居場所がなくなってしまう当事者もいます。可視化が進んでも受け皿を作らないとつらい思いをする当事者もいるので、こういったトランスデーのような場所が必要だと思っています」と話します。
アライの人たちができることは
当事者たちのために設けられたトランスデーですが、扉は様々な人たちのためにも開かれているそうです。
「トランス当事者だけの場所と思う人もいるかもしれませんが、トランスの情報を知ってもらう場でもあり、誰でもウェルカムです」と、浅沼さんは話します。
これまでにも、トランスジェンダーのことを知りたいという人や、自分も何かしたいというアライの人、「授業でトランスジェンダーについて習った」という人など、様々な人たちが訪れたそうです。
そんな時には、スタッフそれぞれが自分の経験をシェアすることもあるといいます。
アライとして、どんなことができるのでしょうか?という質問を、それぞれのスタッフに尋ねてみました。
小林さんが考えるサポートは「アライであることが可視化される努力」をして欲しいということ。
時枝さんは「身近に性別違和を抱えている人がいた時には、1人にせずに声をかけ、ただ寄り添ってあげて欲しい」と話します。

浅沼さんが大事だと思うのは「常に味方でいる」こと。
「トランスの人にもグラデーションがあって、置かれている状況も個々により異なりますし、トランスという属性に入れられることが嫌な人もいます。何に困っているのかどんなサポートをして欲しいのかは一人一人違うので、対話をしながら寄り添って欲しいなと思います」
他にも、トランスジェンダーの人が身近にいるかもしれないということを心がけて会話をするのも大事なことです。
「周りにはいないと断言したような会話や、『オネエって気持ち悪い』というような一言、らしさを押し付けられる会話をされてしまった時、当事者が自分のことを話せない状況になってしまったり、苦痛に感じる可能性もあります。だから、常に視野を広げて会話するのが大事かなと思います」と浅沼さんは言います。
ジャンジさんは「セクシュアリティを自分ごととして捉えて欲しい」と話します。
「LGBTQ+の人たちは、人数が少ないからセクシュアルマイノリティと言われています。本来セクシュアリティは誰もが持っているもの。だから『LGBTQ+の人たちのために何かをしてあげよう』ではなく自分のことの延長線上で『自分とは違う人たちがどうしたら暮らしやすくなるか』ということを、対話をしながらともに考えて欲しいなと思います」

他にも、会話の中でトランスジェンダーの人たちがネタにされた時に「それっておかしいんじゃない」と声をあげる、山谷氏のような差別発言が起きた時に抗議の署名活動に参加する、SNSでトランスジェンダーの人たちについての肯定的なメッセージを投稿する、といった形でもサポートできる、と浅沼さんたちは話します。
「周りで動いてくれる人が増えれば増えるほど、生きやすい社会になると思うので、一緒に行動してくれる人が増えて欲しいなあと思います」
ここから、広がって欲しい
あそこに行けば誰かがいる、あそこに行けば安心してありのままに過ごせる。そんな居場所として、毎月2回開かれているトランスデー。
訪れた人たちからは「こういう場所をもっと早く知りたかった」や「昔、自分がつらかった時にこういう場所があったらよかったのに」という声が寄せられているそうです。
自身も昔を振り返り「こういう場所があったらよかった」と思うという時枝さんは、「ぜひこのトランスデーを色々な人に伝えたり、1人では行きづらいという当事者がいたら一緒に訪れたりして欲しい」と話します。
リアルな場所として続けていく一方で、今後は足を運べない人たちも参加できるオンライン開催や、当事者だけのクローズドの会、トランスジェンダーを知ってもらうためのオープンな会といったイベントも考えているそうです。

また、このトランスデーがロールモデルとなって、同じような場所が全国にどんどん増えて欲しいという願いもあります。
全国の自治体では、まだトランスジェンダーの人たちを支援する体制が整っておらず、悩みを抱えるトランスジェンダーの人たちが自治体の相談窓口を頼っても「トランスジェンダーの人は対応できない」と受け入れてもらえないケースも少なくないそうです。
「一人で抱えこんでいる人も多い中で、その人たちが孤立したり、自死を考えなくていいような社会を用意してあげないといけないと切実に感じます」と浅沼さんは言います。
そのためにも、トランスデーのような場所や自治体の相談窓口が増えることが必要だと感じており、ジャンジさんは「将来的には、自分はここが合うなとか、今月ここがやっているからここに行こうかとかぐらい、選べるまでに増えてほしい」と話します。
プライドハウス東京レガシーでは、毎月第1・3火曜日に、トランスデー行なっています。トランスジェンダー、GID/GD、ノンバイナリー(Xジェンダー)に関連した書籍、チラシや冊子などを設置して、さまざまな情報提供を行なっています。 pic.twitter.com/2KDls1VhE4
— Pride House Tokyo(プライドハウス東京)🏳️🌈 (@PrideHouseTokyo) May 25, 2021
Source: ハフィントンポスト
トランスジェンダーの人たちを孤立させるバッシング。月2回の「トランスデー」はなぜ生まれたのか